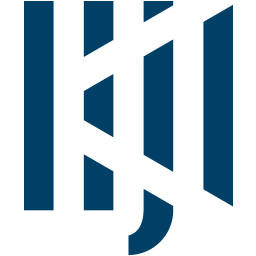KIJIの製品は、木地師と呼ばれる伝統的な工芸技術を継承する職人が手がけています。木地師とは、どのような職人なのでしょうか。ただ木工に携わる職人というだけに留まらず、森と向き合い、育て、共存する姿勢。木を活かすための技術と心が、そこに息づいているように思います。
木地師のルーツ
木地師の歴史は古く、平安時代前期(9世紀)にまで遡ることができます。当時、近江国蛭谷(滋賀県東近江市)で隠棲していた小野宮惟喬親王が綱引轆轤(ろくろ)を考案し、家臣や周辺の杣工に木工技術を伝授したことがそのルーツとされています。
森と、木と、人と。
その後明治時代に至るまでに北陸・中部・東北地方を中心に広く伝わりました。良い木の採れる産地やそれらの木の流通が盛んな地域を移動しながら、その技術も継承されてきたのです。
蛭谷は「木地師発祥の地」とされ、現在も木地師資料館が運営されています。
木地師の仕事
ひとことで言えば、木地師は「木を削って製品の形を作る」ことが仕事です。しかし、実際の仕事はろくろを回すだけではなく、多岐にわたります。
原材料である木を粗挽きしたら、2ヶ月以上かけてゆっくりと乾燥させます。そして乾燥庫から出した木は中挽きを経て、さらに10日間ほどかけて常温に馴染ませます。温められて膨らんだ木を元の大きさにゆっくりと戻す工程です。
こうしてゆっくりと時間をかけて下処理された木を、ろくろと鉋で製品に整形していきます。
木を整え、刃を作る
実は、ここで使う刃物(鉋)も木地師自身が作っています。鋼の焼入れから整形・研ぎに至るまで、木地師の手によるものです。自分で使う刃物を自分で作ることは、木地師の伝統です。
KIJIの製品を手がける工房では、木地の整形だけでなく、さらに漆による仕上げまで全ての工程をカバーしています。